神社やお寺で授かったお守り。長く大切に持ち歩いてきたけれど、そろそろ返納しようと思ったとき、「授与された場所まで行けない」「違う神社に返してもいいのか」と悩んだ経験はありませんか?特に「古いお守り返納違う神社」と検索している方の多くは、正しいマナーやルールを知らずに戸惑っているかもしれません。
この記事では、そんなあなたの疑問を一つずつ解消していきます。違う神社でも返納して問題ないのか、返納する際の注意点やマナー、さらにはどこの神社でも受け付けてもらえるのかといった、実際に気になるポイントを網羅的に解説しています。さらに、近くに神社がないときの対処法や、お守りの出どころがわからない場合の対応、有名神社での事例もご紹介。
読み進めていくうちに、形式だけにとらわれず、自分の信仰と感謝の気持ちに沿った行動ができるようになります。最後には、返納を終えたあとに感じられる「心の整理」も、きっと手に入るはずです。あなたの不安を少しでも和らげるために、ぜひ最後までお読みください。

💡記事のポイント
- 違う神社へのお守り返納が可能かどうかの基本的な考え方
- 他社での返納時に注意すべきマナーや具体的な手順
- 郵送やどんど焼きなど返納先が近くにない場合の対応方法
- 授与元が不明なお守りやお寺のお守りの扱い方
✨ 「感謝は伝えたいけれど、遠くて返納に行けない…」そんな悩み、ありませんか?
役目を終えたお守りをいつまでも持っておくのは、運気の滞りを生むことも。違う神社への返納が可能か、今のあなたの運勢が新しい加護を求めているか、まずはプロに相談してみませんか?
溜まった不運をリセット!今すぐすべき「浄化と手放し」の鑑定(ヴェルニ)
古いお守り返納違う神社でも問題ない?基礎知識と対応法
- お守りは違う神社に返納してもよいのか
- 古いお守りを別の神社に返納する際の注意点
- どの神社でも返納を受け付けてくれるのか
- 返納できる神社が近くにない場合の対処法
- 返納時に必要なお金やのし袋のマナー
- どこの神社のものか分からないお守りの扱い方
お守りは違う神社に返納してもよいのか
お守りは授かった神社やお寺に返納するのが本来の形式とされていますが、実際には違う神社に返納しても問題ないとされています。古くから神社仏閣においては「神仏を敬い、感謝の気持ちを持って返す」という心構えが重視されており、厳密に「授かった場所にしか返してはいけない」という決まりがあるわけではありません。
そもそも、お守りは持つ人の無事や願い事の成就を祈って授与されたものです。その期間が終わった後に感謝の気持ちを込めて返納する行為は、信仰の心を表すものであり、どの神社に返すかという形式よりも、真摯な気持ちのほうが重要と考えられています。例えば、旅行先で受けたお守りを地元の神社に返す人も多く、神社側もそのような事情を理解し、柔軟に受け入れているケースが多いのが現状です。
一方で、各神社の方針によっては「当社で授与したものに限る」と返納を制限していることもあるため、必ずしもすべての神社が他所のお守りを受け入れているとは限りません。そうした神社に返納したい場合は、事前に電話や公式サイトで確認を取るのが無難です。
このように、違う神社にお守りを返納することは一般的に許容されています。ただし、形式だけにとらわれず、返納の際には静かに感謝の気持ちを持って行動することが大切です。
古いお守りを別の神社に返納する際の注意点
古いお守りを別の神社に返納する場合には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。まず最も大切なのは、返納先の神社が「他の神社のお守り」を受け付けているかどうかを確認することです。多くの神社では快く受け入れてくれますが、全ての神社がそうとは限りません。一部では「当社で授与したもの以外はお預かりできません」としている場合もあります。
そしてもう一つは、返納の際のマナーについてです。お守りを返す際には、専用の納め所が設けられていることが多いため、そこに丁寧に納めましょう。紙袋やビニール袋にまとめて入れるのではなく、お守りそのものを取り出して、直接納めるのが基本です。また、返納時にはお賽銭を添えるのが通例とされています。金額に決まりはなく、気持ちとして100円〜300円程度を添える人が多いようです。
返納するお守りの種類にも注意が必要です。例えば、お寺で授かったお守りを神社に返納するのは、本来宗教的な違いがあるため望ましくないとされています。仏教と神道では信仰の体系が異なるため、できる限り寺のお守りは寺へ、神社のお守りは神社へ返すのが礼儀とされています。とはいえ、どうしても元の場所に返せない事情がある場合には、受け入れてくれる神社に相談してみるのも一つの手です。
このように、別の神社に古いお守りを返納する際には、「形式を重んじること」と「相手への敬意を持つこと」の両立が大切です。形式的に正しくても、雑な扱いや無断の返納は神聖な場にふさわしくありません。真摯な気持ちで丁寧に対応することが、何よりも重要です。
どの神社でも返納を受け付けてくれるのか
結論から言えば、多くの神社では他の神社で授与されたお守りであっても、返納を受け付けてくれる傾向にあります。現代では人々の移動が活発になっており、旅先や離れた地域の神社でお守りを受けることも珍しくありません。そのため、柔軟に対応している神社が増えてきたのです。
ただし、すべての神社が同じ方針であるわけではありません。中には「当神社で授与したもの以外の返納はお断りしています」としているところもあります。これは、宗教的な理由というよりは、管理上の問題や地域性によるものが多いようです。返納に対応しているかどうかは、公式サイトで記載されている場合もあれば、現地に掲示されている場合もあります。確認を怠らず、事前に問い合わせておくことで無用なトラブルを避けることができます。
また、神社によっては年始や特別な行事の際にのみ、他社のお守りも受け付ける場合があります。例えば「どんど焼き」などの伝統行事では、多くの古札やお守りをまとめて焚き上げるため、他の神社やお寺のお守りでも受け入れることが一般的です。
さらに、近年では郵送による返納を受け付けている神社も登場しています。遠方で直接訪れることが難しい場合には、こうしたサービスを利用することも一つの選択肢です。ただし、郵送での返納には事前の連絡や手順が必要になるため、各神社の案内に従うことが前提となります。
このように、「どの神社でも必ず返納できる」と断定することはできませんが、多くの神社では信仰の心を尊重し、他社のお守りでも快く受け入れてくれるのが実情です。大切なのは、感謝の気持ちを忘れず、返納先の方針に従って丁寧に行動することです。
返納できる神社が近くにない場合の対処法

お守りを返納したいと思っても、近くに神社がないという方は少なくありません。特に地方に住んでいる方や、高齢で遠出が難しい方にとっては深刻な問題といえるでしょう。そうしたときには、複数の対処法を知っておくことで、無理なく気持ちよくお守りをお返しすることができます。
まず試していただきたいのは、最寄りの神社が本当に「返納不可」なのかを確認することです。小規模な神社であっても、お守りの返納を受け付けている場合があります。常駐していない神社の場合でも、地域の氏子さんや管理団体が定期的に清掃や祈祷を行っていることもあり、返納に対応していることもあります。問い合わせ先がわからない場合は、近隣の市区町村の観光課や宗教法人協会に相談してみると良いでしょう。
どうしても近場に頼れる神社がない場合には、郵送による返納という選択肢もあります。現在では一部の有名神社を中心に、郵送での返納を受け付けているところが増えています。たとえば、伊勢神宮や明治神宮、日枝神社などでは、ホームページに返納方法が記載されており、手順に従って送付すれば問題なく処理してもらえます。郵送の場合は、封筒に「お焚き上げ希望」などと明記し、お守りとともにお賽銭相当の金額(現金書留や郵便為替など)を同封するのが一般的です。
さらに、年末年始や節分、どんど焼きなどの年中行事の際には、地域の仮設神事所や特設ブースで返納を受け付けていることもあります。自治体の広報誌や地域の掲示板に情報が出ることも多いため、こまめにチェックすることで、意外なチャンスを見つけられるかもしれません。
いずれの方法を選ぶにしても大切なのは、「丁寧に返納したい」という気持ちを持ち続けることです。無理に捨てたり雑に扱うのではなく、自分の信仰の形に合った方法を探しながら、納得できる形でお守りを返すことが望ましい対応といえるでしょう。
返納時に必要なお金やのし袋のマナー
お守りを返納するときには、どのようなお金の準備が必要なのか、のし袋を使うべきなのかといったマナーが気になる方も多いはずです。初めて返納する人にとっては、形式を知らないことが不安につながることもあります。ここでは、無理のない範囲で心を込めた返納を行うための基本的なマナーについて解説します。
まず、お守りを返納する際に「必ずお金が必要」という決まりはありません。とはいえ、多くの方は感謝の気持ちとして少額のお賽銭を添えています。これはお焚き上げなどの処分にかかる費用や、神社への敬意を表すための行為とされており、一般的には100円〜500円程度が目安です。金額に厳密な決まりはないため、自分が納得できる範囲で問題ありません。高額を納めたからといって功徳が増すわけではなく、気持ちの表現としての意味合いが強いです。
また、「のし袋」を用意すべきかという点についても、通常は不要です。神社の納札所には、直接お守りを納めるだけで済むケースがほとんどであり、のし袋に入れてしまうと、かえって扱いにくくなってしまう場合もあります。ただし、郵送で返納する場合や、特別な思いがある返納であれば、白封筒に「初穂料」「御焚上料」などと記し、現金書留で送るのが丁寧なやり方とされています。
もう一点、現地で返納する際は、お守りをまとめてビニール袋や買い物袋に入れて納めるのではなく、一つ一つ丁寧に取り扱うことが望まれます。複数ある場合でも、なるべく整理して納めることで、神社側に対する敬意が伝わりやすくなります。
形式ばかりを重視しすぎると返って緊張してしまいますが、要は「感謝を形にする」ことが本質です。のし袋や金額のことで悩む前に、まずは自分の気持ちを整理し、「無事を守ってくれてありがとう」と手を合わせる時間を持つことが何より大切です。
どこの神社のものか分からないお守りの扱い方
お守りを返納したいと思ったときに、どこの神社で授かったのか分からなくなってしまったというケースは意外とよくあります。旅行先や家族・知人から譲り受けたものなど、授与元が不明なまま保管されていたお守りの扱いに迷う人は少なくありません。このような場合でも、焦らず、敬意を持って対応すれば問題ありません。
まず確認していただきたいのは、お守りに記載されている「社名」や「寺名」、あるいは住所などの情報です。多くのお守りには、小さくても由来や場所が記載されている場合があります。文字が消えかけている場合でも、慎重に観察することで判断できる可能性があります。分かる範囲の情報をもとに、インターネットで検索すれば、授与元の神社や寺を特定できることもあります。
それでも特定が難しい場合には、「他社のお守りでも返納を受け付けている神社」に持参するという方法が現実的です。都市部の大きな神社や、多くの参拝客を受け入れている神社では、授与元が不明なお守りでも快く引き取ってくれるところが多くあります。こうした神社では、返納所に「他社のお守りも納めてください」と掲示してあることもあります。
また、返納先に迷った場合は、お住まいの地域の氏神様や総鎮守の神社に相談するのも一つの方法です。氏神様はその土地を守る神様とされており、地域住民の信仰を受け入れる立場にあるため、事情を説明すれば対応してもらえる可能性が高いでしょう。
どうしても気になる場合には、郵送での返納を受け付けている神社に送るのも有効です。授与元が不明である旨を一筆添え、「お焚き上げをお願いしたい」と丁寧にお願いすれば、多くの神社はそれに応じてくれます。
お守りの役目が終わったと感じたとき、最も大切なのは「感謝の気持ちを持って手放すこと」です。出どころが分からなくても、心を込めて対応することが信仰の本質に通じています。決して無理に処分せず、自分なりに納得できる形を選ぶことが望ましいでしょう。
🌀 「手放す勇気」が、次のステージの扉を開く鍵になります。
お守りを正しくお返しすることで、あなたの「魂の空きスペース」が生まれ、そこに新しい幸運が流れ込みます。
これからあなたが手にするべき新しい加護や、挑戦すべきことについて、専門家の具体的なアドバイスを受けてみましょう。
返納後に舞い込む「劇的な好転」と新しい出会いの予兆(ウィル)
古いお守りの返納違う神社での正しい方法と時期・マナー

- 古いお守りはいつ返納するのが良いか
- 正しい返納の方法と神社での手順
- 郵送やどんど焼きでの返納は可能か
- お寺のお守りは神社に返しても大丈夫?
- 有名神社での返納の事例紹介
- 古いお守りを持ち続ける選択肢と意味
古いお守りはいつ返納するのが良いか
お守りは一定の期間、持ち主の安全や願い事の成就を祈ってくれるものですが、永遠に持ち続けるものではありません。では、いつ返納すれば良いのかという疑問に対して、多くの人が「年末年始」や「1年経過したタイミング」を思い浮かべるかもしれません。実際、一般的な目安として「授与から1年」が一区切りとされているのは事実です。
これは、1年という期間が“願掛け”や“ご加護”の効果がひとまず満了する節目とされているためです。特に初詣や節分など、年が変わる時期に合わせて新しいお守りを授かる人が多く、その際に古いお守りを返納する流れが一般的になっています。これはあくまで形式であり、厳密な期限があるわけではありません。
ただ、病気平癒や学業成就、安産祈願など、特定の目的を持ったお守りの場合は、その願いが叶った時点でお返しするのが自然な流れです。たとえば、合格祈願のお守りであれば、進学や合格が確定したタイミング、安産祈願なら無事に出産を終えた時期が返納の目安となります。
また、長年持っていたお守りが色あせたり、破損した場合なども、一つの区切りととらえて返納して問題ありません。破れたり汚れたりしたからといって「不吉」と考える必要はありません。むしろ、それだけお守りが役目を果たしてくれた証と捉え、感謝の気持ちを込めてお返しすることが大切です。
このように、「1年経ったから必ず返さなければならない」と硬く考える必要はなく、自分の中で「一区切りがついた」と感じたタイミングで返納するのが望ましいと言えます。大切なのは期間ではなく、敬意と感謝の心をもって丁寧に手放すことにあります。
正しい返納の方法と神社での手順
お守りを正しく返納するためには、神社での作法や手順を知っておくことが大切です。特別に難しい決まりがあるわけではありませんが、神様に感謝を伝える行為である以上、一定のマナーを守ることが求められます。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、基本的な流れを理解しておくことで、心から納得のいく返納ができるはずです。
まず、神社に着いたら本殿にお参りをしましょう。お守りを納める前に、「これまで守っていただいたことへの感謝」を伝えることが何より大切です。その際の作法は、通常のお参りと同様、二礼二拍手一礼で問題ありません。このタイミングで、お守りに関する感謝の言葉を心の中でそっと添えても良いでしょう。
参拝が済んだら、神社内に設けられている「古札納所(ふるふだのうしょ)」や「お焚き上げ所」に向かいます。場所がわからない場合は、社務所の職員に聞けば案内してくれるはずです。納所には「古いお守りはこちらへお納めください」と表示されていることが多く、そこへ直接納めることで返納の手続きは完了します。
このとき、紙袋やビニール袋に入れたまま入れるのではなく、お守り本体のみを取り出して納めるようにします。複数ある場合は、軽く整理してから入れると丁寧です。また、感謝の気持ちとして「初穂料」や「御焚上料」としてお金を添える人も多く、一般的には100円〜500円程度をお賽銭箱に入れることで十分です。
お守りが神社のお札とセットになっている場合や、破損が激しい場合なども、そのまま納めて問題ありません。神職が後日、まとめて清めてからお焚き上げを行ってくれます。自分で処分することは避け、必ず神社を通じて返納するようにしましょう。
このように、特別な準備が必要なわけではありませんが、「返納する気持ち」と「正しい手順」を意識することで、安心してお守りを手放すことができるはずです。
郵送やどんど焼きでの返納は可能か
お守りを神社へ返納したいと思っても、さまざまな事情から現地へ直接足を運ぶのが難しいという方もいるでしょう。体調や距離、仕事の都合などにより、参拝できないことは誰にでもあります。そういった場合、郵送や地域行事である「どんど焼き」を活用することで、無理のない形で返納することが可能です。
まず、郵送による返納についてですが、近年では一部の神社が正式に対応を開始しています。特に都市部の有名神社では、郵送でのお焚き上げを希望する参拝者が増えたことから、手順や宛先をホームページなどで公開しています。返納の方法は、封筒や箱にお守りを入れ、同封のメモに「お焚き上げ希望」と記載した上で、初穂料(目安として500円〜1,000円程度)を現金書留か郵便為替で送るのが一般的です。
ただし、すべての神社が郵送を受け付けているわけではありません。公式に認めていない神社もあるため、事前に電話やWebサイトで確認することが必要です。また、現金そのものの同封が禁止されている場合もあるため、郵便局での手続きに注意しましょう。
一方、「どんど焼き」は地域の伝統行事として古くから行われてきた返納手段の一つです。主に1月15日前後の小正月に行われることが多く、神社の境内や広場で焚き火を焚き、しめ縄やお守りなどを焼き上げて祈願を納めるという行事です。この場では、家族や地域の人々が持ち寄ったお守りも含めて、まとめて丁寧に焚き上げてもらえるため、個人では対応しにくい方にとって非常に助かる機会となります。
ただし、どんど焼きも地域によって対応が異なり、「神社で授与されたものに限る」「ビニール製品は不可」などの注意事項が設けられていることがあります。事前に自治体の広報誌や地域の掲示板で情報を確認し、ルールに従って参加するようにしましょう。
このように、郵送やどんど焼きを利用することで、直接神社へ出向くことが難しい方でも、正しくお守りを返納することが可能です。どちらの方法においても共通して大切なのは、形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを忘れずに丁寧に対応するという姿勢です。
お寺のお守りは神社に返しても大丈夫?
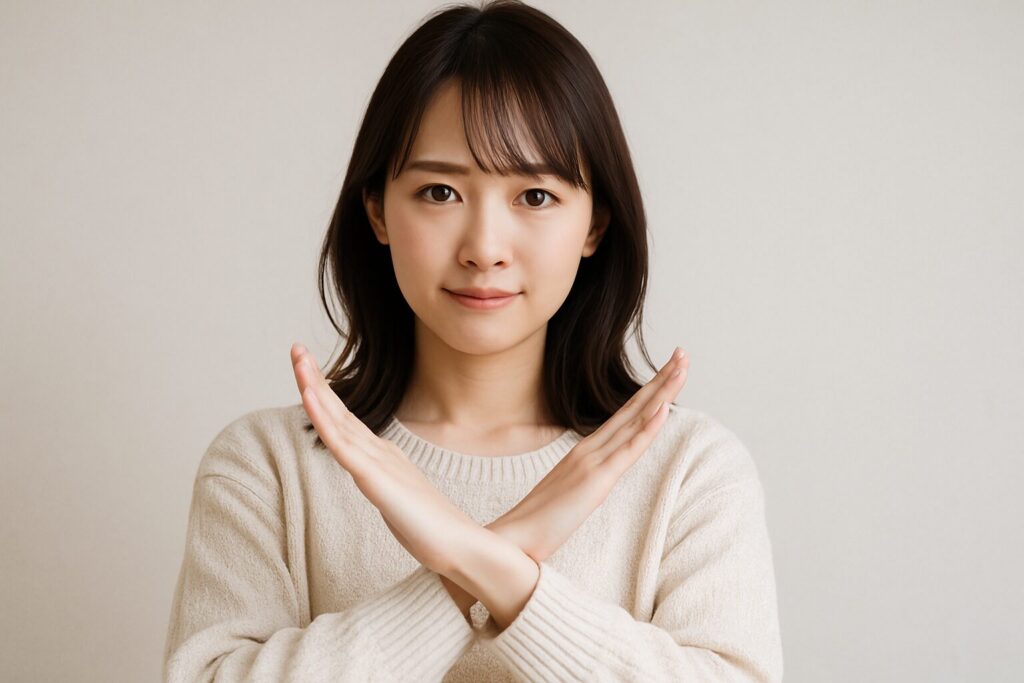
お守りには、神社で授与されるものと、お寺で授与されるものがあります。いずれも持ち主の安全や願い事の成就を祈るものですが、その背景にある宗教的な体系は異なります。神社は神道に基づいており、お寺は仏教の考え方に根ざしています。この違いがあるため、「お寺のお守りを神社に返納してもよいのだろうか」と疑問を持つ方は少なくありません。
実際には、できる限り本来の授与元であるお寺に返納することが望ましいとされています。宗教的な尊重の観点から考えても、それぞれの宗教施設でお守りを清め、焚き上げるのが自然な流れです。例えば、お寺で授かった厄除けのお守りであれば、そのご加護を祈ってくださった僧侶や寺院に感謝を込めて返すことが、より丁寧な対応といえます。
一方で、生活環境や地理的事情により、元のお寺に行けないというケースもあるでしょう。そのような場合、やむを得ず神社に返納するという選択をする方もいます。神社の中には、お寺のお守りであっても「信仰心を持って丁寧に返納していただけるならば受け入れる」としているところもありますが、それはあくまで例外的な対応であると理解しておく必要があります。
また、逆に神社のお守りをお寺に返納することも、仏教の立場から見ると違和感がある行為とされることがあります。それぞれの宗教は別の道を持っているため、できる限り混同せず、個々の信仰体系に配慮することが大切です。
このように、お寺のお守りを神社に返すことは絶対に禁じられているわけではありませんが、基本的には避けるのがマナーです。どうしても返納先が分からなかったり、返しに行けない事情がある場合には、神社に相談して受け入れてもらえるか確認するとよいでしょう。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、相手先や信仰への敬意を忘れずに行動することが、最も重要な姿勢です。
有名神社での返納の事例紹介
古いお守りを返納する場所として、有名神社を選ぶ方も多くいます。理由はさまざまですが、「信頼できる神社で丁寧に対応してほしい」「地元には納められる場所がない」などの背景から、規模の大きな神社や知名度のある神社を訪れる傾向が強まっています。ここでは、実際にいくつかの有名神社で行われている返納の事例を紹介しながら、実態を詳しく見ていきましょう。
まず代表的な存在として挙げられるのが、東京都にある「明治神宮」です。年間を通じて参拝者が多く、初詣の人出は日本一とも言われています。この神社では、境内に設けられた古札納所で、他の神社から授かったお守りであっても丁寧に受け取ってくれる体制が整っています。返納所には案内看板もあり、誰でも迷わず納めることができるよう配慮されています。
また、伊勢神宮(三重県)も全国的に有名な返納先です。伊勢神宮では「お焚き上げ」の儀式を通じて、返納されたお守りや御札を清め、神様にお返しするという丁寧な手順が守られています。ここでは郵送による返納には対応していませんが、現地で直接返納する際には多くの人が訪れるため、非常に整った仕組みが用意されています。
京都の「伏見稲荷大社」も、観光と信仰の両面で人気のある神社です。こちらでも年間を通じて返納が可能で、全国から集まる参拝者の古いお守りを受け入れています。正月期間などの混雑時でも、古札納所はわかりやすく設置されており、誰でも安心して返納できます。
これらの神社では、特に他社のお守りを返納することに対して寛容であるケースが多く、「信仰の心があれば、出どころを問わず受け入れます」という方針が見られます。ただし、すべての有名神社が同じ対応をしているわけではなく、「当社で授与したものに限る」と明示している神社もあります。そのため、事前に公式サイトや電話で確認しておくのが確実です。
有名神社に返納するメリットは、対応が丁寧で安心感がある点にあります。一方で、混雑や待ち時間が長くなる可能性がある点は考慮しておく必要があります。このような情報を知っておくことで、自分に合った返納方法を選ぶヒントとなるでしょう。
古いお守りを持ち続ける選択肢と意味
古いお守りは、一般的には1年を目安に返納することが勧められています。しかし、返納のタイミングには個人差があり、「どうしても手放せない」「思い入れがある」と感じる人も少なくありません。こうした中で、「お守りを持ち続けることに問題はあるのか?」という問いに向き合う人が増えています。
結論から言えば、古いお守りを持ち続けること自体に大きな問題はありません。神道や仏教においても、「感謝の心を持って大切に保管している限り、罰が当たるようなことはない」という考えが根底にあります。むしろ、粗末に扱って捨ててしまうほうが望ましくないとされているのです。
特に、家族の形見として授かったお守りや、困難な時期を乗り越えた象徴としての意味を持つお守りなどは、持ち主にとって特別な存在であることが多いです。こうした場合、「一年経ったからすぐに返さなければならない」と無理に手放す必要はありません。自宅の神棚や引き出しなど、清潔で落ち着いた場所に保管し、定期的に手を合わせることで、お守りの力を尊重し続けることができます。
一方で、持ち続けることで新たなお守りのご利益が受けられなくなるのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。こうした場合は、新しいお守りを授かる際に、古いお守りに「これまでありがとうございました」と心の中で伝えるだけでも十分です。神仏の世界では、形式よりも心のあり方が重視されます。
ただし、物理的に劣化が進んだお守りは、破れたり中身が出てしまうことで不安を感じる原因になることもあります。そうした場合には、「役目を終えた」と自分の中で整理し、神社に返納することで気持ちを新たにするのも良い方法です。
お守りを持ち続けることは、過去の自分を肯定する行為でもあります。守ってもらった経験や支えられた記憶を大切にしながら、今の自分を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。大切なのは、「どう扱えば神様が喜ぶか」よりも、「自分がどう感謝の気持ちを伝えたいか」に意識を向けることです。
🌈 感謝と共に納めることで、あなたの加護はさらに強固なものへ。
返納の不安を解消した今のあなたには、新しい光が差し込んでいます。その輝きを一生モノの運気に変えるために。一度プロの鑑定で、あなたのこれからの運勢を整えておきましょう。
参拝後の「サイン」を詳しく読み解く
強いエネルギーを持つ神社へ参拝した後、不思議な体験や体調の変化を感じた方は多いはず。それは神様からのメッセージかもしれません。今のあなたに届いている言葉を、厳選された専門家に無料で相談してみませんか?
【由緒ある実力派】電話占いヴェルニ全国の有名占い師が集結。格式高い神社にふさわしい本格鑑定を。
初回4,000円分無料で相談する【驚愕の的中率】電話占いウィル「怖いほど当たる」と話題。強い霊感で不思議体験の真相を解明。
初回3,000円分無料で相談する【TVCMで話題】ココナラ電話占い手軽に相談したい初心者の方へ。圧倒的な安心感とコスパ。
最大30分無料で気軽に話す
古いお守り返納違う神社でも安心して対応するためのまとめ

- お守りは本来、授かった神社やお寺に返納するのが丁寧な対応とされている
- 授与元とは異なる神社で返納しても失礼にはあたらず、心を込めて返すことが重視される
- すべての神社が他社のお守りを受け入れているわけではないため、事前確認が重要
- 返納の際には、神社の公式サイトや電話などで受け入れ可否を確認しておくと安心できる
- 古札納所やお焚き上げ箱など、神社が設けた返納専用の場所に納めるのが基本的な手順
- 返納時は、まず本殿にお参りし、守ってくれたことへの感謝の気持ちを伝えるのが望ましい
- お守りを袋ごとまとめて入れるのではなく、1つずつ丁寧に取り出して納めるのが礼儀にかなう
- 処分にかかる費用への感謝として、100〜500円ほどのお賽銭を添える人が多い
- のし袋は基本的に必要ないが、郵送時など特別な場合は白封筒に初穂料と書いて対応する
- 神社に行けない場合は、郵送での返納に対応している神社を探して利用することも可能
- 地域のどんど焼きや節分行事でお守りを焚き上げる場を設けているところも活用できる
- お寺のお守りは、宗教的背景の違いから基本的にお寺に返納するのが適切とされている
- どこで授かったか分からないお守りは、大規模な神社などで相談すれば引き取ってもらえる場合が多い
- 明治神宮や伊勢神宮、伏見稲荷大社などの有名神社では他社のお守りも受け入れていることがある
- 古いお守りは授与から1年を目安に返すのが一般的だが、大切に保管し続けても問題はない
関連記事


